今月17日からは、冬土用期間に入りました。それに伴って病状が悪化した方が急増しています。
冬の寒さと部屋の温度差によるヒートショック、雪の降る地域であれば転倒による骨折、屋根の雪おろし中の転落事故のリスク…冬は危険が身近に潜んでいます。
先日ブログに親族の件を書きましたが、突然の別れは誰でも辛いものです。
冗談めいて「よく不幸が3人続く、というからね。気を付けないと」と母が呟いていたのですが、その矢先に身内の体調が急変し、即入院となりました。とにかく回復を祈るばかりです。
ちなみに日本の田舎の地域には槌引(つちひき)という古い風習があり、年内に2人不幸が続いた場合は3人目が出ないように、2人目の葬式の時に3人目の木槌をつくって棺に入れたり葬列で引きずって歩くそうです。現在も行われているか定かではありませんが、東北地方の民族誌に槌引という言葉が出てくるので、その地域に古くから根付いていた風習だと思います。
なぜ木槌なのか?という点が個人的には気になる所です。
七福神の大黒天は日本の大国主と同一視されますが、その持ち物が打ち出の小槌です。この小槌は、振ると願い事を叶えてくれる福を象徴する縁起物です。福をかき集める熊手にも、恵比寿と大黒天が飾られているのをよく目にしますよね。

打ち出の小槌が願い事を叶えてくれるのなら、槌引の木槌には一体どんな意味合いがあるのでしょうか?これはあくまで私の推測ですが、これ以上死者を出さないようにという願いを叶える、振ったり所持することで良くない流れを断ち切る、という事に繋がるのではないでしょうか。
また、皆さんご存知の平家物語には小槌を持った鬼の話があり、日本の伝承には小槌=鬼の所有物という話が数多く存在します。そうなると、今度は「そもそも鬼の正体はなんなのか?」と疑問が生じます。

鬼は世間一般的には、妖怪、悪い者、といった印象が強いでしょうが、日本では様々な解釈がなされています。霊、祖霊、地霊、神の眷属、強い者の象徴…etc. 鬼の持つ意味はたくさんあるのです。
この中で注目したいのは、鬼=先祖の霊、という考えです。実際に奈良県のある地域では、今もなお「鬼はご先祖様」と代々伝えられている所があります。
槌引きは、小槌を持った先祖の霊(鬼)に「これ以上死者が出ませんように」というお願いをする儀式、という風にも捉えることができるのではないでしょうか。伝承や風習には起源が不明なものが数多く存在するので真偽のほどは分かりませんが、あれこれ考えてしまいます。
さて、今月は気学でいう同期同盤にあたり、誰もが厳しい部分に直面する一月となります。この「厳しい」には様々な意味合いが込められていますが、実践を伴って初めて理解できる事が多いと改めて思いました。今回入院をした親族も、冬土用に入ってから容態が急変しました。
毎年気を付けなければいけないの同盤の月ですが、今月は冬土用も被っているので、普段以上に注意が必要です。特に高齢者、こども、重い病気のある人は気を付けるべきと学んではいましたが、時が経つにつれてその意味が分かってきました。何事も日々実践と鍛錬です。
~あとがき~
秋田県男鹿半島周辺に伝わる「なまはげ」は角があるので鬼だと思っている方が多いのですが、実は鬼ではなく神様なんですってね。なまはげは日本の重要無形民俗文化財に指定されています。









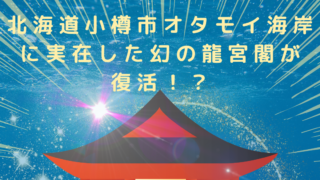






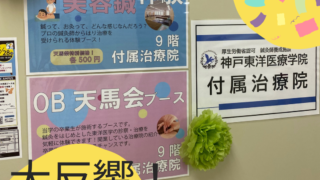





コメント